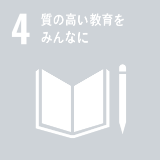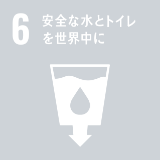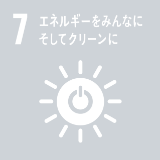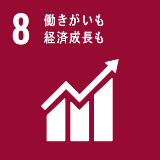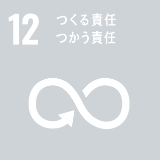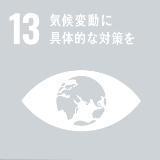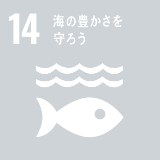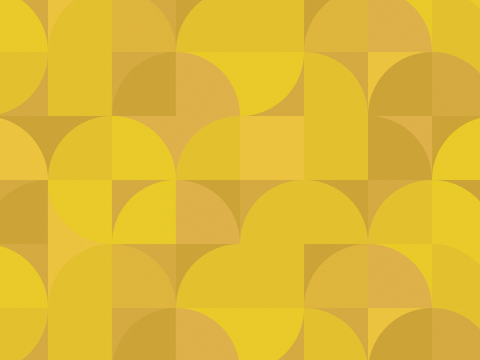佐藤 安信教授
大学院総合文化研究科 地域文化研究専攻
SDGs
連携提案
法律の観点から、地球的規模の課題、たとえば、難民、人権、紛争処理、法の支配、法整備支援などを中心に、非暴力的に持続的平和を実現するための研究をしている。元々15年間弁護士として、UNHCR, UNTAC, EBRDなどで法務、人権担当官をし、カンボジア、ベトナム中央アジア、東欧での法整備支援などにも関わってきた。そのようなバックグラウンドから、地域の実情を踏まえた研究を国際機関や二国間の援助の実践に結びつけ、地域の人々にとっての平和を構築し、逆に、その実践から見えて来る新たな研究課題を考えていきたい。
参画・協力に関心を持つ企業との連携、あるいは関連の課題を持つ企業へのコンサルテーションなどが可能である。
事業化プロポーザル
-
 ベトナムにおける企業活動の紛争処理などについてのコンサルティング近年、中国に替わるアジアの生産拠点であり、統合が進む有望な市場として、ベトナムへ注目が集まり、工場設立や投資を行う日本企業が増えている。また、インフラ整備のための、大型の官民連携プロジェクトに参加を検討している日本企業も多い。しかし、同国では、市場経済に必要な様々な制度が整備途上にある。 特に、ビジネスに関する紛争を適切に処理するシステムが十分でないために、汚職が蔓延する実態もある。この研究室では、同国の透明な紛争解決システムの整備などに協力しており、ベトナムの仲裁センターの仲裁人候補者として同国の紛争処理(仲裁)の事情などに通暁している(2011年1月に発効予定の商事仲裁法の起草でコメントなどをしてきている)ため、現地における経済活動にともなって直面する様々な問題について、適切なアドバイスをすることができる。
ベトナムにおける企業活動の紛争処理などについてのコンサルティング近年、中国に替わるアジアの生産拠点であり、統合が進む有望な市場として、ベトナムへ注目が集まり、工場設立や投資を行う日本企業が増えている。また、インフラ整備のための、大型の官民連携プロジェクトに参加を検討している日本企業も多い。しかし、同国では、市場経済に必要な様々な制度が整備途上にある。 特に、ビジネスに関する紛争を適切に処理するシステムが十分でないために、汚職が蔓延する実態もある。この研究室では、同国の透明な紛争解決システムの整備などに協力しており、ベトナムの仲裁センターの仲裁人候補者として同国の紛争処理(仲裁)の事情などに通暁している(2011年1月に発効予定の商事仲裁法の起草でコメントなどをしてきている)ため、現地における経済活動にともなって直面する様々な問題について、適切なアドバイスをすることができる。 -
 紛争予防・平和構築のためのビジネスモデルに関する研究この研究を提案する佐藤教授は、内外の弁護士事務所や、国連難民高等弁務官事務所、国連カンボジア暫定統治機構、欧州復興開発銀行等、多くの国際機関での実務経験を有し、これらの経験を基に、人間の安全保障、国際協力、紛争と開発、平和構築の研究を進め、現在、「平和構築とビジネス」研究に取組んでいる。(東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム担当、同研究科附属グローバル地域研究機構持続的平和研究センター長) 開発支援やビジネスも、進め方によっては新たな紛争の原因を作ることにもなりかねない。そのため、現地の状況やニーズを的確に把握し、現地の人間・文化・社会の理解・尊重、現地政府との良好な関係の保持、現地法の理解もしくは必要により新たな法整備、ロジスティクス、必要なハードウェアの開発など、多くのファクターを含む総合的な計画のもとに進めることが必要である。また、これらの支援を進めることを通じて現地社会に望まれる貢献を果たしながら、優秀な日本の技術力を生かした機材・機器の供給、公共物の建設、将来の企業進出やマーケット開拓等、ビジネスチャンスを生み出してゆくことも可能である。そのため、国連などが活動をしてきている紛争経験国などへの日本企業の参入を促す必要がある。本研究室では、国連グローバル・コンパクトと連携して、「紛争影響国における責任あるビジネスへのガイダンス」の作成に協力するなどしてきた。
紛争予防・平和構築のためのビジネスモデルに関する研究この研究を提案する佐藤教授は、内外の弁護士事務所や、国連難民高等弁務官事務所、国連カンボジア暫定統治機構、欧州復興開発銀行等、多くの国際機関での実務経験を有し、これらの経験を基に、人間の安全保障、国際協力、紛争と開発、平和構築の研究を進め、現在、「平和構築とビジネス」研究に取組んでいる。(東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム担当、同研究科附属グローバル地域研究機構持続的平和研究センター長) 開発支援やビジネスも、進め方によっては新たな紛争の原因を作ることにもなりかねない。そのため、現地の状況やニーズを的確に把握し、現地の人間・文化・社会の理解・尊重、現地政府との良好な関係の保持、現地法の理解もしくは必要により新たな法整備、ロジスティクス、必要なハードウェアの開発など、多くのファクターを含む総合的な計画のもとに進めることが必要である。また、これらの支援を進めることを通じて現地社会に望まれる貢献を果たしながら、優秀な日本の技術力を生かした機材・機器の供給、公共物の建設、将来の企業進出やマーケット開拓等、ビジネスチャンスを生み出してゆくことも可能である。そのため、国連などが活動をしてきている紛争経験国などへの日本企業の参入を促す必要がある。本研究室では、国連グローバル・コンパクトと連携して、「紛争影響国における責任あるビジネスへのガイダンス」の作成に協力するなどしてきた。